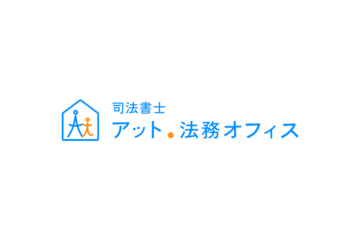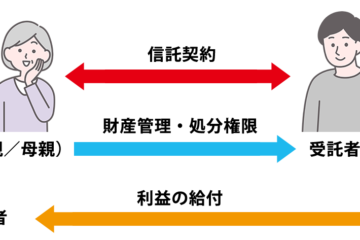遺留分とは?
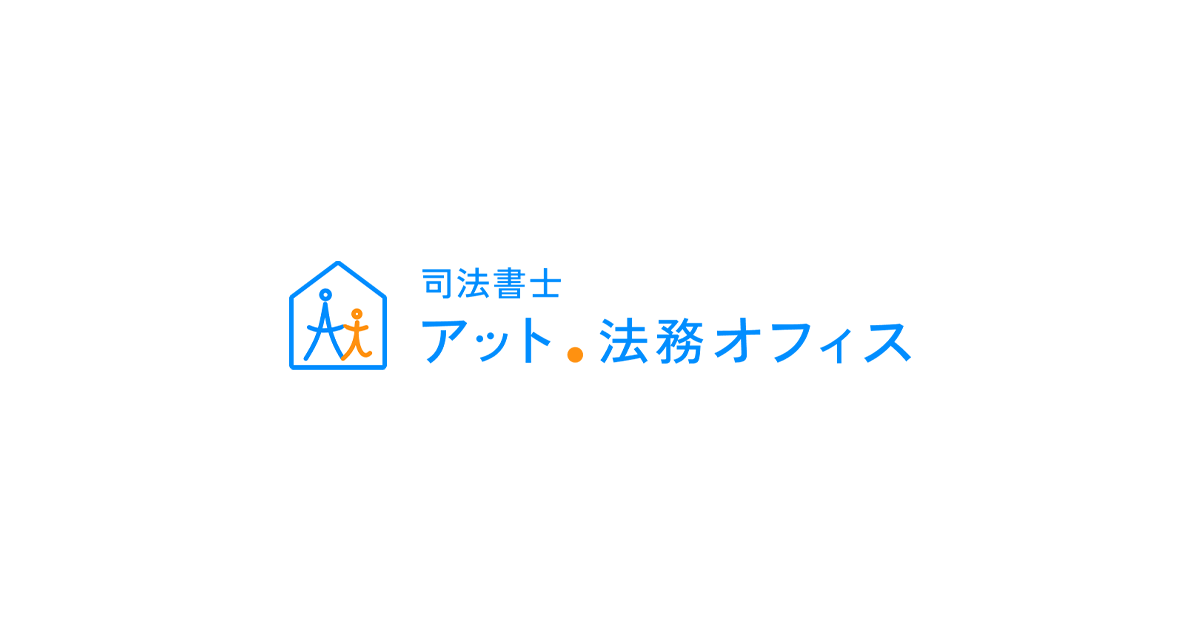
目次
遺留分とは?
「遺留分」とは、一定の相続人に対して認められている、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を最低限譲り受けることができる権利のことを言います。
これは、被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度で、被相続人の意思とは関係なく、遺産の一定の割合の金額を相続人が取得することができます。
この権利を有している相続人のことを「遺留分権利者」と呼びます。
この「遺留分権利者」の範囲は、基本的には被相続人の配偶者・子ども・両親となります。
但し、被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、その子(孫)が代襲相続人として遺留分権利者になります。
また、孫が被相続人の養子となっていた場合にも、遺留分権利者になります。
一方、被相続人の兄弟姉妹や叔(伯)父・叔(伯)母、甥姪には遺留分は認められていません。
では、遺留分の計算方法はどのように考えたら良いでしょうか?
遺留分の計算方法は2段階に分かれていて、まず、遺留分権利者である相続人の全員が有している遺留分の合計額(総体的遺留分)を計算します。
次に、各遺留分権利者が個別に有する割合である「個別的遺留分」を計算します。
(1)【総体的遺留分】・・
①被相続人が独身で配偶者や子どもがなく、遺留分権利者が「両親のみ」の場合は、遺産の3分の1が、
②被相続人に配偶者や子どもがいる場合は、遺産の2分の1が総体的遺留分となります。
例えば、被相続人の遺産が3,000万円だった場合、①の場合は、1,000万円が(両親の)総体的遺留分となります。
また、②の場合は、1,500万円が(配偶者や子どもの)総体的遺留分となります。
(2)【個別的遺留分】・・
個別的遺留分は、
〈総体的遺留分によって算出された金額〉✖〈各遺留分権利者がもつ法定相続分〉で計算します。
例えば、下記を参考にしてください。
遺留分権利者が、
①配偶者のみの場合、
【総体的遺留分】は2分の1で、
配偶者の【個別的遺留分】は2分の1
②配偶者と子どもの場合、
【総体的遺留分】は2分の1で、
【個別的遺留分】は配偶者4分の1・子ども4分の1
③子どものみの場合、
【総体的遺留分】は2分の1で、
子どもの【個別的遺留分】は2分の1
④両親のみの場合、
【総体的遺留分】は3分の1で、
両親の【個別的遺留分】は3分の1
⑤配偶者と両親の場合、
【総体的遺留分】は2分の1で、
【個別的遺留分】は配偶者6分の2、両親6分の1
⑥配偶者と兄弟姉妹の場合、
【総体的遺留分】は2分の1で、
兄弟姉妹には遺留分が無いため、
配偶者の【個別的遺留分】は2分の1
⑦兄弟姉妹のみの場合、
兄弟姉妹には遺留分が無いため、
総体的遺留分も無し。
分かりずらいですよね・・。
以下、より具体例を挙げてみます。
具体例①
遺留分権利者が配偶者と子ども2名で、被相続人の遺産が2,000万円だった場合・・
【総体的遺留分】は1,000万円で、
【個別的遺留分】は配偶者500万円・子ども2名で500万円(1人につき、250万円)。
遺留分に該当しない残りの1,000万円が被相続人の自由な意思で遺贈や寄付に使える金額となります。
具体例②
遺留分権利者が配偶者と父母で、被相続人の遺産が3,000万円だった場合・・
【総体的遺留分】は1,500万円で、
【個別的遺留分】は配偶者1,000万円・父250万円・母250万円。
◎では、自身の遺留分が侵害された場合に、遺留分権利者はどのように遺留分を請求すれば良いのでしょうか?
①まず、他の相続人や遺言により遺産を譲り受けた人(受遺者)と話し合いをします。
この段階で遺留分の支払いに対する合意が取れれば「合意書」を作成し、自身の遺留分に対する支払いを受けて終了です。
② ①で合意できなかった場合、内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」を送ります。
ここで内容証明郵便にしておく理由は、遺留分侵害額請求には、『※時効』があり、その時効を止めることができるからです。
③ ②でも合意できなかった場合には、最終手段として地方裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を起こすことになります。
この訴訟で遺留分権利者の訴えが認められれば、裁判所が相手方に対して支払い命令を出すことになります。
※『時効』について・・
遺留分侵害額請求には、〈相続の開始及び遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わなければならない〉という時効があります。
自身の両親と疎遠であり、相続開始の事実を知らない場合でも、遺言書が遺されていれば、遺言執行者から相続開始の事実が知らされます。
また、遺留分権利者が行方不明で、相続開始から10年間が経つと「除籍期間」があり、遺留分の請求はできなくなります。
◎最後に・・
遺留分は、遺留分権利者にとって非常に強い権利です。遺留分の請求をされた場合には、基本的にその請求に応じなければなりませんので、遺言者や他の相続人が遺留分の存在を知らなかった場合、相続手続きの中でトラブルになる可能性があります。
そのため、ご自身の相続や遺言書の作成について考える際には、遺留分について留意し、適切に理解したうえで準備されることをおススメ致します。
相続や遺言書の作成について、ご不安な点やご質問がございましたら、お気軽にアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理