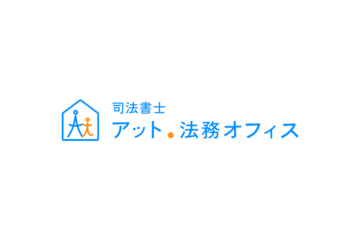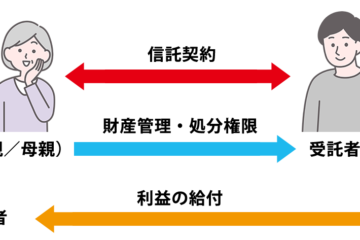子供がいない夫婦の相続で困らないために
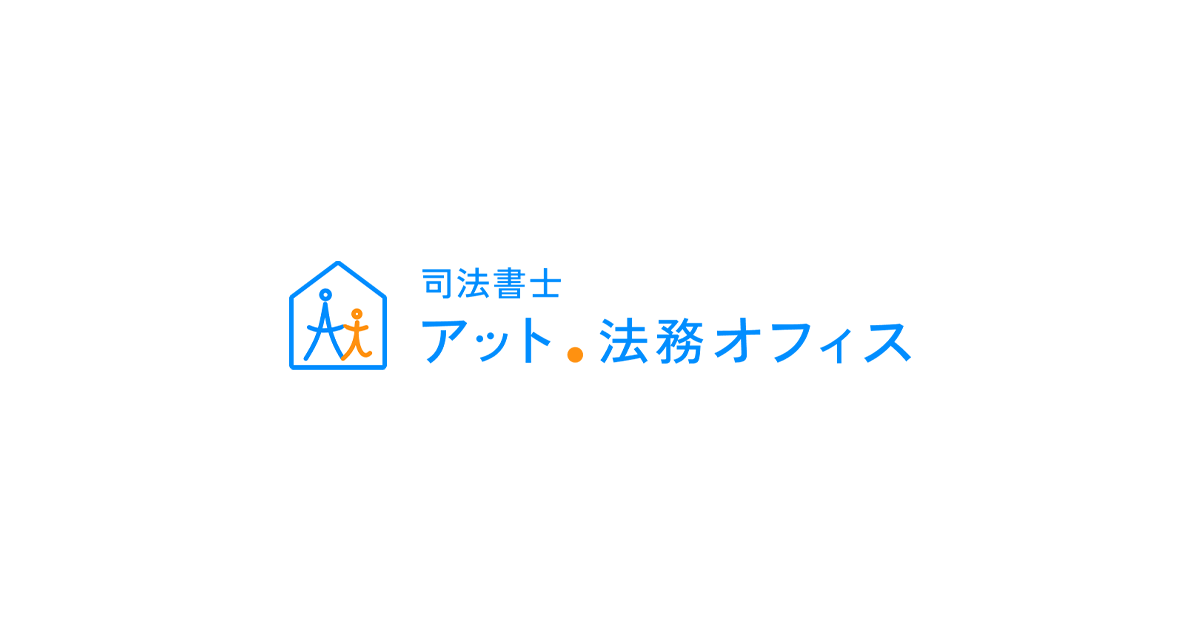
目次
子供がいない夫婦の相続で困らないために
夫婦の内、夫が先に亡くなったとき、子供がいれば妻と子供が相続人になります。
一方、子供がいない夫婦の場合は、夫が先に亡くなったとき、妻のみが相続人になるのでしょうか?
結論から言うと、この場合、妻のみが相続人になるとは限りません。
妻の他に、亡き夫の両親や兄弟姉妹、甥や姪までもが相続人になる可能性があります。
具体例を挙げてみると、子供がいない夫婦の場合、以下の順番で相続人になる人が決まります。
①夫の両親が生きていれば、相続人になります。この場合の法定相続分は、妻が3分の2、両親が3分の1です。(両親が共に生きていれば、6分の1ずつになります。)
②夫の両親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、代襲相続により、その子、すなわち夫の甥や姪が相続人になります。この場合の法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹(甥や姪)が4分の1になります。
つまり、子供がいない夫婦の相続では、亡き夫の妻と両親が共に相続人になったり、妻と兄弟姉妹、甥や姪が共に相続人になったりする可能性があるのです。
子供がいない夫婦で配偶者(夫や妻)だけが全財産を相続できるのは、両親が共に亡くなっていて、兄弟姉妹もいない場合のみです。
そして遺産を分けるときには相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、全員で話し合いをしなければなりません。
ここでもし、亡き夫の妻と、夫の甥や姪が共に相続人となり、あまり付き合いがないと、遺産について話し合いをすることが精神的な負担になるのではないでしょうか?
夫の生前、付き合いが無かった甥や姪でも、自分に相続する権利があると知ってその権利を主張してくることは当然あります。
特に遺産が、分割することが難しい不動産であると、分け方を巡って争いになってしまうことがあります。
Q.では、子供がいない夫婦が遺産分割のトラブルを防ぐためには、何をしておけば良いでしょうか?
A.この場合、遺言書を作成しておくことが最善な方法です。遺言書を遺しておけば、法定相続よりも遺言書が優先します。
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要が無く、亡き夫の両親や兄弟姉妹、甥や姪と話し合いをしなくても良いのです。
遺言書作成時の注意点・・
①亡き夫の両親が相続人となる場合、両親には遺留分がありますので、遺言書を書く時には「遺留分」に注意してください。全財産を妻に譲ると遺言書に書いていても、両親が生存していれば、遺留分を請求される可能性があります。このような場合には、両親にも遺留分相当の財産を譲る旨の遺言書の内容にすることを検討した方が良いかも知れません。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、気にする必要はありません。
②遺言書は夫婦別々に作成しましょう。
人はいつどこで亡くなるか分かりません。
もちろん夫が先に死亡するとは限らず、妻が先に死亡することもあります。
③遺言書は公正証書にしておきましょう。
遺言書は一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がよく利用されますが、公証役場で「公正証書遺言」にしておく方が良いでしょう。
自筆証書遺言はご自身で手軽に書くことができますが、方式を間違えると無効になるリスクがあり、自身亡き後に家庭裁判所の検認を受ける手間が発生してしまいます。
公正証書遺言は、公証役場で公証人の面前で作成しますので、無効になるリスクは考えにくく、検認を受ける必要も無いので、相続手続きをスムーズに進めることができます。
◎まとめ・・
子供がいない夫婦の一方が亡くなり、疎遠な親族と共に相続人となった場合、話し合いが上手くまとまらず、遺産分割でトラブルが起こる可能性があります。
そうならないように「遺言書」を公正証書にして遺しておいてください。
遺言書の作成を考えている方、或いは相続発生後、疎遠な親族との話し合いに不安を感じている方は、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理