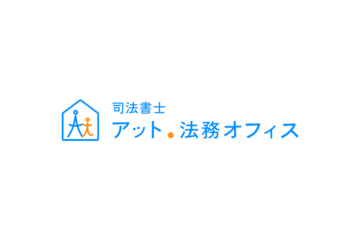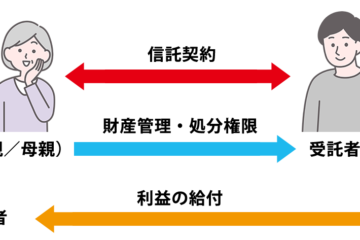相続人の一部の協力が得られない場合には?
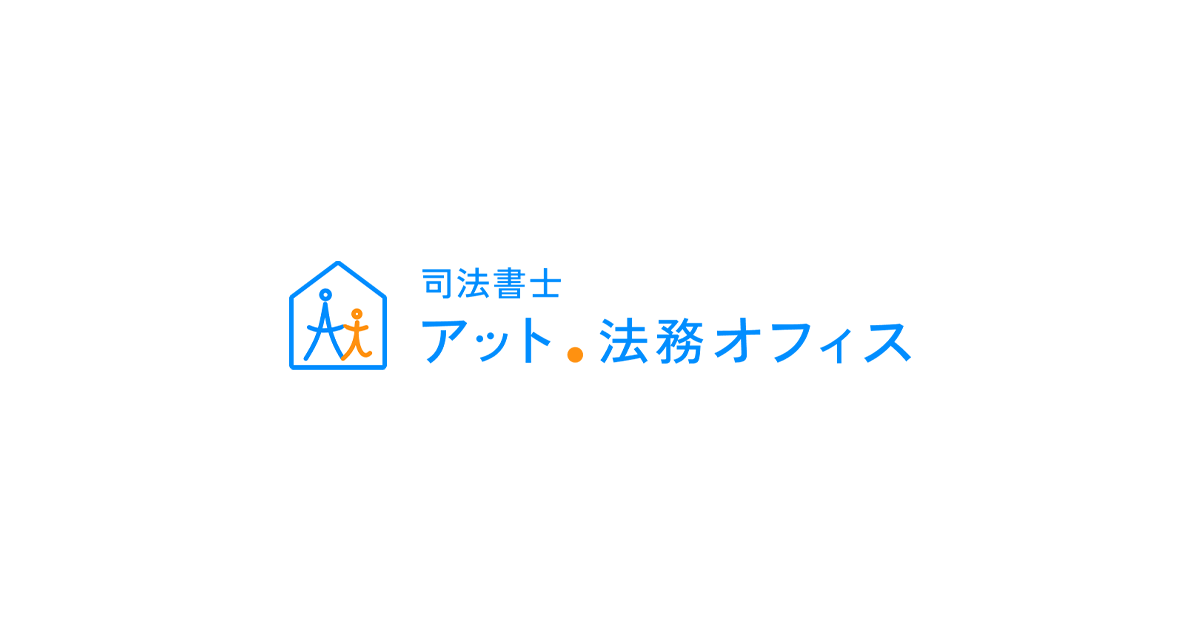
目次
相続人の一部の協力が得られない場合には?
相続が発生し、相続手続きをする際には、「相続人全員」の協力が必要になります。
例外として、故人が遺言書を遺していて財産の譲受人を指定している場合には、相続人全員に連絡を取る必要はなく、遺言書に基づき手続きを進めることができます。
しかし、その他の場合には、故人が所有していた不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しなどを行う際には、必ず「相続人全員」で遺産分割協議を行わなければなりません。
つまり、相続が発生し、遺言書が無い場合には、疎遠な相続人にも連絡を取る必要があるのです。
しかし、普段付き合いのない疎遠な相続人に連絡しても、協力が得られない場合があります。
協力が得られない理由は様々でしょう。
例えば、「相手方が高齢のため、相続の内容が理解できない」や「入院していて、そもそも書類を受け取っていない」、「付き合いがないのに面倒なことに関わりたくない」、「遺産分割の内容に納得できない」、「振込詐欺のような類なのではないかと疑っている」等が考えられます。
では、このように相続人の一部から協力が得られない場合の対策として、どのようなことに気をつければ良いでしょうか?
いくつか挙げてみたいと思います。
◎最初にこちら側から行うべきこととして、
①相続の内容を包み隠さず、まずは手紙で事情を説明する・・
相手方の電話番号がわかるならば、事前に「相続に関する書類を送りますので、確認のうえ連絡が欲しい」旨を伝えてから手紙を送る方が印象が良いかと思います。
そして、遺産の種類や額、各相続人の法定相続分などを明確にして手紙で説明しましょう。ここが不明瞭かつ不誠実だと、最初から相手方に不信感を持たれてしまい、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。
ここで注意して頂きたいのは、普通郵便ではなく、書留等の郵便で送付した方が、相手方も重要な書類と認識して受け取ってくれるでしょうし、こちら側からすれば、相手方が受け取ったかどうかの確認ができます。
また、今後も連絡を取る手段として、こちらの連絡先を明記することも忘れないでくださいね。
②期限を設定する・・
相続税がかかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に申告をしなければなりません。
そうでなくても期限を設けないと放置されてしまうこともありますので、いつまでに折り返しの連絡をして欲しいかの期限をきちんと伝えるようにしてください。
◎それでも協力を得られない場合には、
①相手方が手紙をそもそも受け取っていない場合には・・
入院などで長期的に不在にしている可能性がありますので、事情を知っていそうな親族に確認するか、直接訪問してみるのも良いでしょう。
②相手方が面倒がっている場合には・・
相続手続きに非協力的な場合には、相続放棄の制度を説明し、相続放棄を促すのも良いかも知れません。
③相手方が遺産分割の内容に納得がいっていない場合には・・
まずは、どうしてそのような分け方をするのかを丁寧に説明し、よく話し合ってください。
それでも協力を得られない場合には、最終的には家庭裁判所の調停や審判で解決しなければならず、お互いに余計な手間と費用がかかってしまい、不利益が生じることを伝えましょう。
◎最後に・・
どうしても協力を得られない場合には、我々司法書士に相談してください。
こちらからの連絡を放置していたり、面倒がっている相続人も、国家資格のある専門家から連絡を受けると、対応しようかという気持ちになることが多いです。
相続手続きを進めていくと、普段付き合いのない親族や関係性が良くない親族に連絡をしなければならない場合があります。
家庭裁判所の調停や審判での解決はなるべく避けたいでしょう。
そうなる前に、相続人の一部の方の協力を得るのが難しそうだと感じましたら、なるべくお早めにアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理